相続した農地が休耕ではなく、放置され荒れ果てているところも多い。
周辺の農地を耕作する農家からすれば、放置されて原野と化した農地は野生動物のすみかにもなって耕作物を荒らしてしまう。
これまでは、農地を取得できるのは現在農業を営む”農家”に限定する農地法があった。
数㎡という家庭菜園では物足りない、1反(300㎡)くらいの畑を耕したい、という人はいるだろうが、農地法3条の「面積500㎡以上の農地保有者」という面積規定は農家以外の一般人が農地を取得できないハードルとなっていた。
令和5年農地法改正により、農地取得の面積要件は廃止され、市町村農業委員会の判断に任されるようになった。
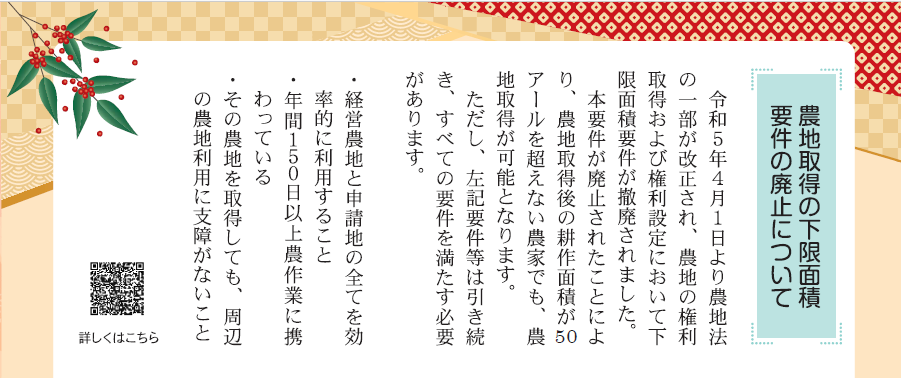
面積要件はないものの、「年間150日以上農業を行う」という条件は設定されている。
この規定を旨く適用すると、過疎化した地域の空き家住宅+農地が、
「晴耕雨読を希望するリタイア夫婦」の終の棲家になりうる のだ。
もちろん、空き家住宅付農地に限定されるわけではないから、少し規模のある農地を耕作したい「家庭菜園族」にも朗報だ。
もっとPRすれば、首都圏に住む多くの高齢者の中には、やる気のある人が出てくるのではないか。
「住むところはあるものの、やることがない」
「自分の食べるものは自分で作りたい」
「農作業をして体を動かしたい」
高齢者が3割近くになった現代には様々なニーズがあるが、偏った情報しか流れない都市住民には、求める適切な情報が流れない
同じような情報だけを流すマスコミに頼らず、各人が求める情報を得やすくなるのがそもそものネット社会である。
google検索は、過去の検索履歴から類推した答えだけを表示するのではなく、思いがけない検索結果も得られるように「クッキーを無視する」設定ボタンが欲しいものだ。
国交省の発表している「農地付空き家の手引き」鑑定業者情報(国交省2015登録順)鑑定業者情報(国交省2015登録順)